「鬼王」の名がつく稲荷鬼王神社(新宿区)

新宿区の地図を見ていると、歌舞伎町のなかにあった「鬼」の名がつく神社が目に止まった。
新宿で知られている神社と言えば花園神社しか思い浮かばず、歌舞伎町といえば有名な繁華街というイメージだけだったので、ほかに神社があるとは思ってなかった。
そこで、どんな神社なのか興味を持ったので、
繁華街として有名な歌舞伎町にある神社

稲荷鬼王神社へ行くと、神職さんが境内を清掃していた。
私に気づくと、掃除の手を止めて、神社の由来が書かれたリーフレットを手渡し、簡単に説明してくれた。
稲荷鬼王神社の社殿と境内のようす

神職さんの話のよると、稲荷鬼王神社は、歴史のある神社で文化財となっているものもあるという。
小さな境内だったが、きれいに整備されていて、大事にされている感じが伝わってくる神社だった。
神獣オオカミ

神社の説明をしながら境内を案内してくれた。
鳥居の近くには神獣がいて、ごつい狛犬だなと思っていたら、オオカミだと教えてくれた。
また、神社に「稲荷」がつくけど、境内には稲荷様はいないとのことだった。
社殿の前には狛犬

社殿の前には狛犬もちゃんといた。
狛犬を見ると、玉を大事そうにくわえている子獅子がいて、可愛らしかった。
また、もう片方の狛犬は、子獅子が親のヒゲにかみついてじゃれていたので、クスッとなった。
新宿区の文化財となっている水鉢

鬼の頭上に水鉢――という珍しい彫刻もあった。
新宿区の文化財に指定されているこの水鉢には、説明板があって、次のように書かれていた。
鬼王神社の水鉢
新宿区指定有形文化財 彫刻
文政年間(一八一八~一八二九)の頃制作されたもので、うずくまった姿の鬼の頭上に水鉢を乗せた珍しい様式で、区内に存在する水鉢の中でも特筆すべきものである。
水鉢の左脇には、区内の旗本屋敷にまつわる伝説を記した石碑があり、これによると、
「この水鉢は文政の頃より加賀美某の邸内にあったが、毎夜井戸で水を浴びるような音がするので、ある夜刀で切りつけた。その後家人に病災が頻繁に起こったので、天保四年(一八三三)当社に寄進された。台石の鬼の肩辺にはその時の刀の痕跡が残っている。……」
とある。
この水鉢は、高さ一メートル余、安山岩でできている。
平成五年一月/東京都新宿区教育員会
◇
どうやら、文化財となっている水鉢には、鬼が毎夜水浴びをしていたという不思議な伝説があるようだ。
水琴窟

境内には水鉢のほかにも珍しいものがあり、水をかけた後に竹筒へ耳を近づけてみると、心地よく響く水滴の音を聞くことができる「水琴窟」が2か所あった。
富士塚

社殿の横には、浅間神社もあり「西大久保の厄除け富士」とも言われているらしい。
富士塚があったが、神職さんの説明によると、戦争前は今よりも大きかったようで、戦争があったためいろんな経過をたどって、現在は二つに分かれた形となった珍しい富士塚とのことだ。
稲荷鬼王神社で入手した由来記
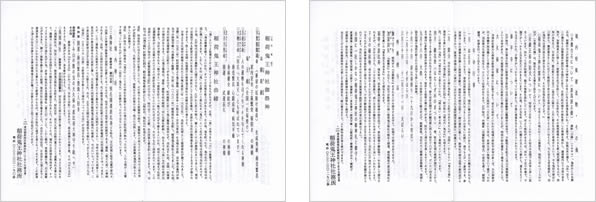
新宿の繁華街に、歴史のある神社があるとは思っていなかったので驚いた。
それに、運良く神職さんから稲荷鬼王神社についての歴史などを聞くことができたので面白かった。
また、稲荷鬼王神社では、境内の掲示板に古い映画のポスター展示をしていたり、不定期だが新宿区にゆかりのある小説家(小泉八雲や島崎藤村など)の本を展示をするなどのイベントもやっているようだ。
稲荷鬼王神社周辺のMAP
稲荷鬼王神社(所在地 東京都新宿区歌舞伎町2-17-5)
■稲荷鬼王神社までの距離(徒歩の場合)
最寄り駅
・東新宿駅…約 0.235km(02分)
・西武新宿駅…約 0.689km(08分)
・新宿区役所…約 0.509km(06分)
観光情報についての参考サイト
■新宿区
公式サイト
■GO TOKYO
東京の観光公式サイト